この記事でわかること
本記事では、マーケティングにおける「アラインメント(アライメント)」の意味と役割について、その基本的な概念から現場での課題、そしてどのように実践的に活用・強化できるかを詳しく解説しています。マーケティング部門と営業部門が連携できていない場合に生じる具体的な問題点や、組織間の認識ギャップが経営に与える影響を理解できるほか、顧客情報やデータの統合、共通KPIの設定、ABMやインサイドセールスの活用といった最新の改善策も紹介しています。これらを通して、アラインメントが企業全体の業績向上や競争力強化に不可欠な戦略であることがわかり、自社での連携強化や組織改革に向けた具体的なヒントを得られる内容となっています。
アラインメントとは何か?

アラインメント(Alignment)は、BtoBマーケティングにおいて、マーケティング部門とセールス(営業)部門の連携や整合性を指す重要な概念です。これは単に部署間の連携を意味するだけでなく、マーケティング、営業、製品開発などの関連部署が「有機的に結びつく」ことによって、組織全体の成果を最大化し、「部分最適」ではなく「全体最適」を目指す取り組みを表しています。
語源の英語「Alignment」は「一列に並べる」「調整する」「協力」「団結」などの意味を持ち、マーケティングと営業が同じ方向を向いて、顧客への価値提供を一気通貫で行う姿勢を象徴します。こうした調整がなければ、部門間の行動にズレが生じ、ビジネス機会の損失や効率低下が起こりやすくなります。
つまり、アラインメントとは企業の成長を支える、マーケティングと営業活動の“架け橋”であり、最も重要な経営戦略の一つです。
なぜアラインメントが必要なのか──多くの組織が直面している課題と機会損失
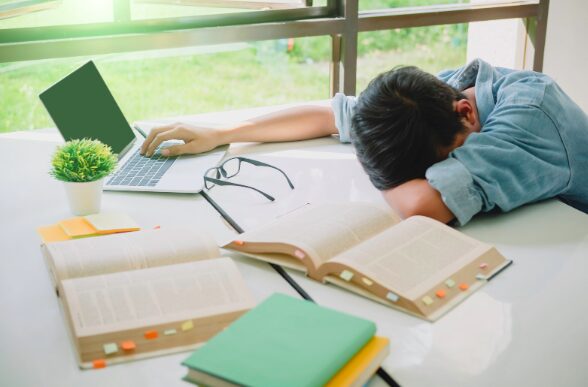
現代の変化の激しい市場環境の中で、企業は多様なチャネルと多段階のマーケティング施策を駆使し、潜在顧客を獲得し育成しています。しかし、そうしたマーケティング施策で獲得・育成した見込み客(リード)を、営業がしっかりと成約に結びつけられなければ、投資コストの回収もできず、ビジネス成長は停滞します。
マーケティング部門は顧客獲得や啓蒙活動に多大な時間とリソースを投じていますが、営業との連携が弱ければ、生成したリードが活用されず放置されてしまうことも少なくありません。これにより、企業全体としては以下のような多重損失が発生します。
- リード獲得・育成の効果が見えにくくなり、マーケティングROIが悪化。
- 営業は効果の薄いリードに時間を割き、本来見込める案件への注力も阻害される。
- 顧客に対して一貫した体験やメッセージを届けられず、企業イメージの低下につながる。
このように、マーケティングと営業がバラバラの方向を向き、組織内で機能不全が起きることは、競合が激化する現代では致命傷となります。
そこでアラインメントは、部門間の壁を取り払い、“お互いの動き方・役割を理解・尊重して一体化する”ための必須ステップとして注目されています。
アラインメントが取れていない場合の具体的課題
マーケティング部門における課題
アラインメントが十分に機能していない企業では、マーケティング部門側で以下のような問題が顕著です。
- 獲得したリードが営業で活用されず放置され、努力が無駄になると感じる。
- リードの質や量の洞察を営業と共有できず、施策の効果測定や改善が難しい。
- マーケティング施策の売上貢献度を正確に把握できないため、戦略立案の根拠が不十分。
結果としてマーケティングは孤立感を強め、営業成果との連動が取れずに業務効率が下がってしまいます。
営業部門(セールス)における課題
逆に、営業現場では以下のような不都合や不満が生まれやすいです。
- 質の低いリードが多く渡され、営業活動の能率が下がっていると感じる。
- マーケティングの取り組み内容や成果が把握できず、信頼関係が築けない。
- 自身の実績評価や生活が直接改善されないまま数だけ増えるリードに対応に追われる。
こうした課題はモチベーション低下や離職率増加の原因にもなりかねません。
また、両部門間の認識ギャップが解消されない限り、顧客への価値提供も一貫しないため、トータルな顧客体験の質が損なわれるリスクがあります。
アラインメントを阻む主な原因
1. 分断されたシステムとデータ管理
多くの企業では、マーケティングが独自に管理するデータベースと営業が使用するCRMやSFAが統合されておらず、顧客情報が分断されています。このため、情報や履歴の共有が困難で、顧客を包括的に管理・追跡できません。
例えば、同一顧客に対して重複した営業連絡が発生したり、顧客の最新ニーズに応じた最適な対応ができないことがあります。これが連携不全の根幹的な課題です。
2. 部門間の文化・認識ギャップ
マーケティングと営業でKPIや評価基準が異なると、互いの活動が理解されにくくなります。特に日本企業で見られる縦割り・部分最適志向の組織風土は、異なる目標を追う部門間の連携を阻害しやすいです。
その結果、マーケティングは数値重視でリード数を追い、営業は個人商談や顧客対応に注力し、双方が「お互いの仕事が見えない」と感じ、コミュニケーション不足により不信感が増す悪循環に陥ります。
日本企業の現状とアラインメントの重要性の高まり

日本ではこれまで、展示会、広告、テレマーケティング、Webプロモーションなど多種多様なマーケティング施策が縦割りで行われるケースが多く、全体として戦略的に練られたアラインメントは進んでいませんでした。そのため、活動の重複や顧客の取りこぼし、部門間の責任不明確化による効率損失が頻発していました。
しかし、昨今はデジタルマーケティングの普及とCRM・MA(マーケティングオートメーション)ツールの普及もあり、多くの企業でマーケティングと営業のデータ連携や情報共有が強化され、戦略的なアラインメント実現への取り組みが加速しています。
経営トップも認識する課題として組織横断的なプロセス整備やツール統合、コミュニケーション推進が行われ、よりシームレスで効果的な顧客対応体制が構築されています。
アラインメント強化に有効な最新手法・事例

1. CRM・MAツールのシームレス連携
マーケティングオートメーション(MA)と営業支援システム(CRM/SFA)のデータ連携は、アラインメント強化のキーです。たとえばマーケティング側で獲得した見込み客の温度感や活動履歴がリアルタイムで営業に共有されることで、営業はタイムリーかつ的確なアプローチが可能になります。
さらに顧客ジャーニー管理が一元化されることで、双方で成果の把握やプロセス改善の議論がしやすくなっています。
2. 共通KPIの策定と定期的な連携ミーティング
マーケティングと営業の双方が共感し合える共通指標(例:リードの質評価、案件の商談化率、成約率)を設定し、定期的にレビュー会議を行うことも効果的です。これにより両部門は互いの期待値や課題を共有しやすくなり、認識のズレを逐次調整できます。
組織文化としての協働意識が醸成され、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながります。
3. ABM(アカウントベースドマーケティング)の導入
ABM戦略は特にBtoB企業でのアラインメント強化に威力を発揮します。あらかじめターゲット企業や決裁者プロファイルを明確に設定し、マーケティングと営業が一体となって対応することで、無意味なリードの乱発を防げます。ターゲットに絞ったパーソナルかつ効果的なアプローチを可能とし、営業の無視率を下げる成果が確認されています。
4. インサイドセールス、ADR(Account Development Representative)の設置
営業とマーケティングの間にインサイドセールスやADRポジションを置き、マーケティングが育成したリードを一度精査・ナーチャリングしてから営業に渡す運用も増えています。これにより、営業の負担軽減とリードの商談化精度向上が両立し、結果的に双方の負担軽減とアラインメント促進を実現しています。
まとめ:アラインメントの今後の展望と経営戦略上の位置づけ
アラインメントは単なる業務の調整ではなく、「マーケティングと営業の連携を通じた企業成長の推進力」として不可欠な戦略的要素です。顧客接点を一枚岩とし、多くのチャネルと情報源からのデータを統合管理しながら、一貫したメッセージと顧客体験を創出することが現代ビジネスの必須要件です。
今後の日本企業の競争力強化には、アラインメントを紐解き・改善する取り組みが内部変革の中核となるでしょう。最新のデジタルツールと組織文化変革を融合させ、全社横断的に顧客志向のプロセスを設計し、実行することで、持続的な成長とブランド価値の最大化を実現してください。
ぜひ本記事を参考に、自社のマーケティングと営業間のアラインメントを戦略的に見直し、強化へ向けた具体的な一歩を踏み出していただければ幸いです。

コメント